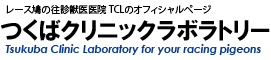最近の若鳩病の情報 2024
若鳩病(Young Pigeon Diseases=YPDS)は古くから知られる主に1歳未満の若い鳩に発症する伝染病のことです。
臨床症状の主体は腸炎で、嘔吐、下痢、食欲不振、体重減少、脱水、無気力、羽毛が立つなどが特徴です。胃腸炎が起こり消化不良が急激に起こることから嗉嚢から下部消化管に餌が送られなくなり、嗉嚢に餌がたまり、これが持続すると発酵してそ嚢炎と呼ばれる症状が起きます。嗉嚢が異常を起こすのは二次的な所見です。
若鳩病は鳩レース界に深刻な影響を及ぼしてきた鳩の主要疾患の一つです。この疾患は、鳩レースや観賞鳩展示会などの競技期間中に季節的に発生することが多いため、国際的な健康問題ともなっています。しかし、鳩に感染するウイルスは複数以上存在し、我が国で発生している嘔吐や脱力を主張とする若鳩病の原因については未だに決定しきれない状況です。
2018年、オーストラリアのブリスベン北部で繁殖用のハト28羽が死亡する発生が報告された。感染した鳩の症状は鼻水を伴う体調不良だった。2羽が調査のためブリスベンのバイオセキュリティ科学研究所に送られ、一連の診断検査で多くの既知の病原体が除外され、結果的に細胞培養でもウイルスは分離されなかった。組織病理学的検査では、肝臓に重度の急性多巣性壊死が見られ、肝細胞とクッパー細胞に好酸球性核内封入体が認められた。遺伝子の配列検査(HTS)により、鳩アデノウイルス1型(PiAd-A)とハトトルクテノウイルス(PTTV)の全長配列が明らかになった。この報告は、オーストラリアで鳩のアデノウイルス1型(PiAd-1)とハトトルクテノウイルスの混合感染が起こっていること示している。(https://doi.org/10.1007/s00705-021-05033-x)
2024年には劇症肝炎の経過をたどったハトの死体から鳩アデノウイルス1型を分離した報告がある。(https://doi.org/10.1637/aviandiseases-D-24-00002)疫学的調査により、鳩アデノウイルス2型(PiAdV-2) はドイツで広く蔓延しており、若バト病を発症するハトだけでなく、健康なハトにも見られることが示されています。
最近の研究では、若鳩病の主な原因は鳩ロタウイルスA型、遺伝子型G18Pであることがわかってきました(Rubbenstroth et al., 2019 ; Rubbenstroth et al., 2020)。ロタウイルに関連する若いハトの致命的な病気は、オーストラリア、ヨーロッパ、米国で報告されています。ほとんどの場合、ハト型ロタウイルスは全身感染を引き起こし、鳥の肝臓に壊死を起こす。RVAの感染は鳩舎全体に急速に広がり、通常は100%にも達する高い罹患率と、0%から50%を超える死亡率を引き起こす。通常、感染した群れの病気の経過は約 1 週間で、回復したハトが体重を回復するには最大 3 週間かかる。鳩ロタウイルス感染の臨床症状には、無気力、食欲不振、粘液性の緑色の下痢、嘔吐、うっ血した食道などが含まれます。
(疫学的調査により、鳩アデノウイルス2型(PiAdV-2) はドイツで広く蔓延しており、若バト病を発症するハトだけでなく、健康なハトにも見られることが示されています ( Teske et al., 2017 )。
鳩サーコウイルス:PCR を用いたドイツの研究でハトの肝臓に88.00% の割合でサーコウイルスが存在することを 報告した。中国のZhangらは、 PCR 検査を用いて中国で平均75% のハトに 鳩サーコウイルスを発見した。ハンガリーのCságolaらは、ハンガリーで検査されたハトの 57% が鳩サーコウイルス陽性と判定されたが、そのうち 53% は無症状だった。スロベニアでの感染ハトの調査では鳩サーコウイルスの有病率は 74.3% であったという。ポーランドのStenzelらによる研究では、ポーランドの70%以上のハトがPCR検査でPiCV陽性だった。このように、健康なハトも 鳩サーコウイルス(PiCV) に感染していることから、鳩アデノウイルス2型(PiAdV-2) または 鳩サーコウイルス(PiCV) が若鳩病の主たる原因ではないのではないかとする研究もある。
著者には嘔吐と消化器症状を主張とする一般的な若鳩病がサーコウイルスによって起きているとは考え難いが、免疫抑制などを介して関与している可能性は否定できない。とにかく本邦での発生は獣医学的に調べられていません。
最近の研究では、ファイバー 2 遺伝子の特性に基づき、特異性、感度、再現性を備えた鳩アデノウイルス2型検出用の TaqMan-qPCR 法が開発され、これを用いた解析データから、若鳩病と鳩アデノウイルス2型感染の間に相関関係の兆候は見られないことが示唆された。鳩アデノウイルス2型はハトのいたるところに存在しますが、その病原性は不明のままであり、ハトにおける他の病原体との相互作用は非常に複雑であり、さらなる研究が必要です。(https://doi.org/10.1016/j.psj.2024.103848)
鳩アデノウイルスAとサーコウイルスの混合感染で若鳩病が起きているとする論文もある。
私自身の経験に基づいてわかっていることは次の通り。
1)胃腸炎型:日本で発生してきた嘔吐や緑便を主張とする病気はもっとも普通の若鳩病で、これは消化管感染の制御や消化剤の投与で治っていく。適切な治療をすれば1週間ほどの間に症状は軽快する。しかし、症状の回復後にレースに参加させると未帰還鳩が多くなる。これは消化器の症状の回復後にも内蔵機能の回復が完全に回復していないことを意味しているのだろう。
2)肝炎型:1)の標準的な若鳩病の発生の中で、消化器病の治療だけでは回復していかない鳩が一定程度いる。これらは肝炎を起こしていることが知られている。こういった鳩は食欲廃絶が続いて痩せて死亡する。肝炎で症状が重い鳩の回復はほとんど見込めない。一般的な胃腸炎型の発生が起きる鳩群の一部(数羽)にだけ肝炎型が起こる理由は明らかではない。
3)肝炎型の発症が多発する型:これまで胃腸炎型の発生がおきた鳩群の中で10数羽~30数羽の死亡が起きた例がある。これらの解剖はされていないが、死亡原因は急性肝炎だと推察される。これがアデノウイルスによるものか、ロタウイルスによるものかは調査研究が十分ではない。
肝炎型の死亡が多発する発生においては鳩アデノウイルスと 鳩ロタウイルスA型、遺伝子型G18Pの混合感染が起きている可能性もあります。感染が重なって重くなるという事もあれば逆もあります。それは2種類のウイルスが感染する場合、ウイルスの干渉現翔ということが起こり、一方のウイルスの増殖を抑制する現象です。これは近い種類のRNAウイルス感染で起こることが多いですが、DNAウイルスでも起こることが知られています。
対策:若鳩病と呼ばれるのは、一度感染発症すると再度の発症が起こらないためですが、この背景には感染免疫が生じて二度目の感染が抑えられるということです。これは経験的に明らかです。
これまでの経験則から、秋のレース前に自鳩舎の成鳩と若鳩を混ぜて訓練を行うと、他厩舎の鳩との接触がなくとも軽度の嘔吐症状などを見ることがあり、その時に従来からのアデノウイルス感染処方(TCLではそう呼んでいます)を投薬すると速やかに回復して、合同訓練やレース開始後に嘔吐などのいわゆるアデノウイルスの発症を起こさなくなります。
この方法は従来のアデノ感染には有効ですが、鳩ロタウイルスA型など新手のウイルス感染が混じってくると、旧来のアデノウイルス対策では防ぎきれないかもしれません。とはいうものの、この方法で多くの鳩舎はレース開始時の発症トラブルを回避してきています。
我が国ではこれらのレース鳩のウイルス感染について鳩レース実施団体が、獣医大学などに研究予算を提供して調査研究をしてもらうという努力はなされていません。鳩のレースをこれからも継続していくならば、この感染の研究をきちんと進めていく必要があるのではないでしょうか。(この原稿は加筆改変される可能性がある仮のものです。参考にしてください。獣医学博士 百溪)